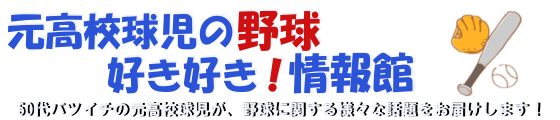こんにちは、当ブログの管理人、元高校球児のみっつです!
ノムさんこと野村克也さんは、プロ野球で通算2901本ものヒットを打った強打者でした。
そんなた野村さんが、ある選手の向かって「お前がいなかったら、俺は3000本打っていた」とボヤいたというエピソードがあるそうです。
ある選手とは、当時の阪急ブレーブスでショートを守っていた大橋譲選手です。大橋選手は広い守備範囲でヒットになりそうな打球を見事に処理して、野村さんをボヤかせたのでした。
今回はオリックスバファローズ背番号6番の歴史について辿っていきます。前身球団を含めて6番をつけてきた全選手と、私が特に気になった3選手、さらに6番の選手の特徴にも触れますので、楽しみにしてくださいね
■目次(クリックすると飛びます)
歴代の背番号6番を背負った選手をご紹介
まずは、オリックスバファローズ歴代の背番号6番を着けた選手を「阪急~統合前まで」・「近鉄~統合前まで」そして「統合後」と3ブロックに分けてご紹介します。
| 旧阪急 | |||
|---|---|---|---|
| 年 度 | 年 数 | 球 団 名 | 選 手 名 |
| 1936年 | 1年 | 阪急軍 | 渡辺敏夫選手 |
| 1937年春~1937年秋 | 1年 | 阪急軍 | 空白 |
| 1938年春 | 0.5年 | 阪急軍 | 野上清光選手 |
| 1938年秋~1942年 | 5年 | 阪急軍 | 石井武夫選手 |
| 1942年 | 0.5年 | 阪急軍 | 義川泰造選手 |
| 1943年 | 1年 | 阪急軍 | 仁木安選手 |
| 1944年~1945年 | 2年 | 阪急軍 | 空白 |
| 1946年~1948年 | 3年 | 阪急軍~阪急ベアーズ~阪急ブレーブス | 上田藤夫選手 |
| 1949年~1952年 | 4年 | 阪急ブレーブス | 明石武選手 |
| 1953年~1954年 | 2年 | 阪急ブレーブス | 酒沢成治選手 |
| 1955年~1956年 | 2年 | 阪急ブレーブス | 片山嘉視選手 |
| 1957年~1959年 | 3年 | 阪急ブレーブス | 畠中良雄選手 |
| 1960年~1971年 | 12年 | 阪急ブレーブス | 石井晶選手 |
| 1972年~1982年 | 11年 | 阪急ブレーブス | 大橋穣選手 |
| 1983年~1984年 | 11年 | 阪急ブレーブス | バンプ・ウイルス選手 |
| 1985年~1991年 | 7年 | 阪急ブレーブス~オリックスブレーブス~オリックスブルーウェーブ | 熊野輝光選手 |
| 1992年~2001年 | 10年 | オリックスブルーウェーブ | 田口壮選手 |
| 1995年~1996年 | 2年 | オリックスブルーウェーブ | 勝呂壽統選手 |
| 1997年 | 1年 | オリックスブルーウェーブ | 空白 |
| 1998年~1999年 | 2年 | オリックスブルーウェーブ | ハービー・プリアム選手 |
| 2000年~2001年 | 2年 | オリックスブルーウェーブ | ジョージ・アリアス選手 |
| 2002年 | 1年 | オリックスブルーウェーブ | 空白 |
| 2003年~2004年 | 2年 | オリックスブルーウェーブ | 塩谷和彦選手 |
| 旧近鉄 | |||
| 年 度 | 年 数 | 球 団 名 | 選 手 名 |
| 1950年~1951年 | 2年 | 近鉄パールス | 島方金則選手 |
| 1952年~1953年 | 2年 | 近鉄パールス | 樋口貞一選手 |
| 1954年~1960年 | 7年 | 近鉄パールス~近鉄バファロー | 原勝彦選手 |
| 1961年 | 1年 | 近鉄バファロー | 谷野信次郎選手 |
| 1962年~1966年 | 5年 | 近鉄バファローズ | 島田光二選手 |
| 1967年~1975年 | 9年 | 近鉄バファローズ | 安井俊憲選手 |
| 1976年~1983年 | 8年 | 近鉄バファローズ | 石渡茂選手 |
| 1984年 | 1年 | 近鉄バファローズ | 空白 |
| 1985年~1986年 | 2年 | 近鉄バファローズ | バンボ・リベラ選手 |
| 1987年~1994年 | 8年 | 近鉄バファローズ | 金村義明選手 |
| 1995年 | 1年 | 近鉄バファローズ | 空白 |
| 1996年~1997年 | 2年 | 近鉄バファローズ | 久保康生選手 |
| 1998年~1999年 | 2年 | 近鉄バファローズ~大阪近鉄バファローズ | 空白 |
| 2000年~2003年 | 4年 | 大阪近鉄バファローズ | 武藤孝司選手 |
| 2004年 | 4年 | 大阪近鉄バファローズ | 空白 |
| 統合後 | |||
| 年 度 | 年 数 | 球 団 名 | 選 手 名 |
| 2005年 | 1年 | オリックスバファローズ | 塩谷和彦選手 |
| 2006年~2008年 | 3年 | オリックスバファローズ | トム・デイビー選手 |
| 2009年~2010年 | 1年 | オリックスバファローズ | 大村直之選手 |
| 2011年 | 1年 | オリックスバファローズ | 金子圭輔選手 |
| 2012年~2014年 | 3年 | オリックスバファローズ | 高橋信二選手 |
| 2015年~ | オリックスバファローズ | 宗佑磨選手 |
旧阪急では背番号6番を背負った選手の歴史は16代に渡ります。
初代・渡辺敏夫選手は阪急軍が創設された1936年に入団するも戦死された内野手です。2代目・野上清光選手は左打のショート。1938年シーズンでは6番打者を多く務めています。
3代目・石井武夫選手はキャッチャーでしたが、時にはファーストとして試合に出場もしました。4代目・義川泰造投手は半年だけ6番を着用し、その後9番へ変更しました。
5代目・仁木安外野手は一度プロを退くも再び復帰した選手です。後に社会人野球・松下電器の監督を務め、阪急・オリックスOB会名誉副会長にも選出されました。
6代目・上田藤夫選手は二遊間を守った選手です。4番打者も務めました。7代目・明石武選手は投手としてプロ入りするも、1試合登板したのみで内野手へ転向。ユーティリティープレーヤーとして活躍されました。
8代目・酒沢成治選手は今なお残る日本記録保持者です。その記録とは「シーズン最少三振」。1シーズンで喫した三振がわずかに6個!これは読売ジャイアンツ・川上哲治選手と共に並ぶ記録です。社会人・日本楽器の監督も務められました。
9代目・片山嘉視選手は2年、10代目・畠中義雄選手は3年で引退した選手です。共に内野手でした。
11代目・石井晶選手は勝負強い打撃でチームに貢献した右打者です。日本シリーズに強く、通算32打数11安打、打率.344を残しています。
12代目は前項でご紹介した大橋穣選手です。
阪急ブレーブス黄金時代の昭和50年代、正遊撃手を務めていた大橋穣選手の最大の特徴は「並外れた強肩」でした。肩の強さに絶対の自信があった大橋選手は、敢えて深めの守備位置を取りました。本人が「12球団のレギュラー遊撃手の中で一番深い守備位置にこだわった」と語るほどに。
普通の遊撃手が深く守れば、打者はその分走る時間を確保できますから内野安打になる確率が高くなります。しかし大橋選手が守備に就いていれば矢のような送球が飛んでくるのでアウトになってしまうのです。
13代目はバンプ・ウイルス選手です。二塁手として起用されていましたが、当時の上田利治監督と反りが合わず、入団2年目の1984年シーズン途中で退団しました。ちなみにこの年チームは優勝、同期入団のブーマー・ウエルズ選手は3冠王でMVPに輝きました。
14代目は熊野輝光選手です。1985年、打率.295 14本塁打60打点で新人王を獲得した左打ちの外野手です。巨人にトレードされましたが後に古巣へ復帰しました。引退後はコーチ、スカウトとして活動しました。
15代目は田口壮選手です。元々は内野手でしたがイップスが原因で外野手へ転向しました。
イチロー選手、本西厚博選手との外野陣は「鉄壁」と称賛されました。のちにMLBへ移籍、独特の存在感で、アメリカのファンの心をもがっちりと掴みました。
16代目は、阪神からいせきしてきた塩谷和彦選手です。阪神時代の1998年からオリックス移籍後の2004年まで塩谷選手が所属したチームが7年連続最下位という巡り合わせの悪さが話題となったこともありました。
続きまして近鉄編です。近鉄の背番号6番は11代続きました。
初代は島方金則選手でした。社会人野球出身で、主にショートを守った右打者です。プロは2年で引退、その後は社会人・日本コロムビアでプレーした後社業に就きました。
2代目・樋口貞一選手は二塁手です。新球団・トンボユニオンズ移籍後はスタメン機会に恵まれました。
3代目・原勝則選手は明治大出身・社会人野球経由の捕手です。1955年には正捕手の座を掴みますが、1960年限りで引退しました。4代目・谷野信次郎選手は1年で背番号を38番に変えさせられた内野手です。
5代目・島田光二選手は内野のユーティリティープレーヤーでした。13年に渡り近鉄一筋で引退。引退後はコーチや解説者として活躍しています。1973年には代理監督を務めたこともありました。
6代目・安井智規選手もユーティリティープレーヤーとして活躍した選手です。1968年には盗塁王を獲得しました。
7代目・石渡茂選手はいわゆる「江夏の21球」でスクイズを外された打者として名前を憶えている方も多いのではないでしょうか。後に巨人でもプレーしました。
8代目・バンボ・リベラ選手は近鉄らしい「三振か、ホームランか」を絵にかいたような選手です。1年目は31本塁打したものの打率は.244。2年目には各チームに研究され、打撃不振のまま6月に解雇となりました。
9代目は金村義明選手です。現在でもバラエティー番組で活躍中ですが、近鉄時代は強打の三塁手、高校時代は夏の甲子園優勝投手でもあります。
10代目は久保康生投手です。元々は近鉄のドラフト1位で、阪神タイガースにトレードされていたものの、1996年に復帰します。前回在籍時より10番少ない6番を着けてのプレーとなりました。
最後11代目は武藤孝司選手です。走力とミート力、そして守備におけるスローイングの評価の高かった遊撃手でしたが、肩を故障してしまい、30歳という若さで引退したのは惜しまれました。
最後は統合後に背番号6番を着けた選手を紹介しましょう。
初代は、旧阪急から引き続いて塩谷和彦選手がつけました。
2代目はトム・デイビー投手。こちらは広島東洋カープからの移籍選手です。手元で微妙に変化するストレートを武器に、カープ時代は達成できなかった2桁勝利を移籍1年目にクリアしました。
3代目・金子圭輔選手もソフトバンクからの移籍選手です。ユーティリティープレーヤーとして欠かせない存在でした。
4代目・高橋信二選手もこれまた移籍組です。元々は北海道日本ハムファイターズの正捕手でしたが、打力を活かして内野手に転向しました。
その後、巨人移籍を経てオリックス入りしましたが、日本ハムで4番を務めていた打力は蘇りませんでした。
そして5代目は、ギニア人の父を持つ現役の宗祐磨選手です。元々は内野手(遊撃手)でしたが、高校時代に141㎞/hを記録したこともある強肩、50メートル5秒8の俊足を活かし外野手に転向しました。
歴代背番号6番のうち、印象深い3選手のご紹介
オリックスバファローズの背番号6番をつけてきた選手のうち、私が印象深く思う金村選手、熊野選手、そして田口選手をご紹介したいと思います。
金村義明選手
出身地 兵庫県宝塚市
投/打 右/右
プロ野球歴
近鉄バファローズ(1982年~1994年)
中日ドラゴンズ(1995年~1997年)
西武ライオンズ(1997年~1999年)
タイトル等 オールスター出場1回
バラエティー番組などで楽しいトークを繰り広げ、人気を集めている金村氏ですが、高校時代から野球選手として素晴らしい実績を残してきました。
兵庫・報徳学園高のエースで4番として、1981年夏の甲子園を制したのですが、その対戦相手には後にプロ入りする選手が沢山いました。
3回戦では荒木大輔選手の早稲田実業高、準々決勝は藤本修二投手擁する今治西高、そして準決勝では工藤公康選手の名古屋電気高を破っての全国制覇しています。
しかも金村選手は1回戦から決勝まで全6試合を完投した上、4番打者としては22打数12安打で打率.545!本塁打も2本放つなど、投打に大活躍でした。この他、春の選抜大会では大府高・槙原寛己投手と投げ合ってもいます。
ドラフト会議に際しては地元の球団である阪急入りを熱望するも、くじ引きで近鉄が交渉権をえるとすんなりとプロ入りしました。すぐさま内野手に転向し、2年目の1983年には早くも初本塁打を記録するなどその実力を徐々に開花させていきます。
1986年には全130試合に出場、打率.275 23本塁打67打点を記録しました。当初は7番だった打順も6番、そしてシーズン終盤には5番に定着。近鉄を代表する選手へと成長を遂げました。
入団当初の28番から背番号を6番に変更した1987年も全試合出場を果たします。成績は若干下がったものの、正三塁手の座は渡しませんでした。
1988年、シーズン終盤に左手有鈎骨を骨折してしまい、いわゆる「10.19」には出場していません。しかし、当時の仰木彬監督の配慮で第2試合はベンチ内に入り、チームに声援を送り松付けました。
1989年は前年の骨折の影響、1990年後半にはルーキーの石井浩郎選手の活躍で出番が少なくなります。それでも1990年には監督推薦でオールスターに出場したり、1991年には再び全試合出場を果たすなど、主力選手として活躍します。
球団が中村紀洋選手を育成する方針を決めたことを受け、1995年に中日ドラゴンズへFA移籍しました。
しかし、ケガ等もあり活躍の機会は少なく、1997年シーズン途中で元チームメートである小野和義投手との交換トレードで西武ライオンズへ移籍します。ここでも活躍の場は多くはありませんでしたが、1997年から2年連続で日本シリーズへ出場するという幸運に恵まれました。
現役引退後、野球解説者を希望したものの、現役時の豪快なイメージからか所属先が決まらないと、金村氏は自費で各球団のキャンプ地を巡り、独自の取材を開始します。話術の巧さもさることながら、しっかりと現場で取材しているからこそ金村氏のトークは人々を引き付けるのでしょう。
近年のテレビ番組では不摂生がたたりこのままでは余命1年と警告されてしまった金村氏。まだまだ楽しいお話を聞きたいので、くれぐれも健康には気を付けていただきたいです。
熊野輝光選手
出身地 香川県木田郡三木町
投/打 右/左
プロ野球歴
阪急ブレーブス~オリックスブレーブス~オリックスブルーウェーブ(1985年~1991年)
読売ジャイアンツ(1992年~1993年)
オリックスブルーウェーブ(1994年)
タイトル等 新人王・ベストナイン1回
熊野選手は、香川県・志度商高時代は実に34年ぶりにチームを甲子園へ導いたことが話題になりました。出場した1975年春の選抜大会では、後に広島東洋カープで抑えの切り札として活躍する小林誠二投手擁する広島工高に惜しくも敗退してしまいます。
大学は中央大へ進学、元東京ヤクルトスワローズ監督の小川淳司選手とチームメートとなります。4年生時の1979年には大学日本選手権を制し、その年のドラフト会議ではヤクルトから3位指名を受けるも拒否。社会人・日本楽器へ入社しました。
1984年、公開競技ながら金メダルを獲得したロサンゼルスオリンピックの野球チームの主将を務めました。この時のチーム全20人中何と16人が後にプロ入りを果たしますが、熊野選手も阪急ブレーブスから3位指名を受け、27歳でプロへ入団しました。
社会人野球で5年間揉まれた実力は伊達ではなく、ルーキーイヤーの1985年、「7番・センター」で開幕スタメンに抜擢されると、そのままレギュラーに定着しました。
打率.295、14本塁打、60打点に13盗塁を記録、新人王に選出されます。阪急としては前年の藤田浩雅捕手に次ぐ、2年連続の新人王輩出となりました。
3年連続で2桁本塁打を記録し、1987年には打率.291を記録するなどレギュラーの座を死守してきた熊野選手でしたが、1988年後半からはジュニアオールスターでMVPを獲得した藤井康雄選手が台頭してきます。
さらにチーム名がオリックスとなった1989年には南海ホークスから門田博光選手が移籍してきました。それに伴いDH専門だった石嶺和彦選手が守備に就くようになり、外野の定位置争いは一気に激化します。
1991年後半からは期待の大型大砲・高橋智選手もその片鱗を見せ始め、出番の少なくなった熊野選手は1992年、勝呂壽統選手との交換トレードで読売ジャイアンツへ移籍しました。
巨人でもスタメン機会は少なく、代打が主となります。移籍2年目の1993年にはほとんど出場機会はなく、半ばコーチ的な役割を担っていました。
1994年、古巣オリックスに復帰するも一軍出場機会はないまま引退となりました。
引退後は打撃コーチとして「がんばろう神戸」のオリックス2連覇に貢献したのちスカウトに転身しました。2000年のドラフト会議では巨人を熱望していた敦賀気比高・内海哲也投手を担当。ドラフト指名を拒んだ経験を持つ身として、内海投手を慮る姿が印象的でした。
田口壮選手
出身地 兵庫県西宮市
投/打 右/右
プロ野球歴
オリックスブルーウェーブ(1992年~2001年)
セントルイス・カージナルス(2002年~2007年)
フィラデルフィア・フィリーズ(2008年)
シカゴ・カブス(2009年)
オリックスバファローズ(2010年~2011年)
タイトル他 ベストナイン1回・ゴールデングラブ賞5回・オールスター出場4回
田口選手は、関西学院大では名ショートとして、また打っても2019年現在も連盟記録として残る通算123安打を記録、走攻守揃った選手として、1991年のドラフト会議の注目選手でした。
そんな田口選手の獲得を阪神タイガースが熱望すると、「阪神へ入団したくない10か条」なる文章を記者会見で読み上げ、阪神の選手・ファンらを激怒させてしまいます。
しかし、この行為は田口選手の阪神への入団を快く思わない大学関係者が仕組んだものと言われ、プロ入り後の田口選手のプレーぶりも印象改善に役立ちました。
田口選手がFA宣言した時は阪神が獲得の意思を示し、結果としてMLB移籍を選択した田口選手が会見で手を挙げてくれた阪神球団にお礼を述べるなど、両者の関係にわだかまりはなくなりました。
プロではショートとしてではなく、外野手として大成する事となります。入団当時の土井正三監督の厳しい指導によってイップスを発症したためと言われました。同期入団のイチロー選手とともに強固な外野陣を形成しました。
打つ方では優勝した1995年は1番イチロー選手、3番田口選手、連覇した1996年にはイチロー選手が3番に固定されると1番打者を務め、打率は.280前後ながら安定しており、リードオフマンとして十分な成績を残しています。
2001年FA権を行使し、MLBセントルイス・カージナルスへ移籍しました。安定した成績こそ残していたものの、突出した実績のない田口選手の移籍にはネガティブな意見もありました。
移籍3年目の2004年、控え選手ながら109試合に出場、179打数52安打、打率.291を記録すると、その万能ぶりが名将・トニー・ラルーサ監督の目に留まります。
翌2005年には143試合に出場、114安打を放ち、打率.288。本塁打も8本放つなど打撃でも注目を浴びます。チームの主砲・アルバート・プホルス選手が休養した試合では3番を打つこともありました。
2006年には開幕スタメンに起用されます。この年チームは世界一を達成し、田口選手はその瞬間をグラウンドで迎えた、初の日本人選手となりました。
2008年には移籍したフィラデルフィア・フィリーズが世界一になりました。田口選手は2個目のチャンピオンリングを手に入れます。
2010年にオリックスへ復帰を果たしました。2年間プレーした後、2011年限りで退団、現役続行の道を模索しましたがオファーはなく、2012年に引退を表明しています。
2016年、オリックス二軍監督として指導者デビュー、2019年からは一軍総合コーチとして西村徳文監督を支えています。
常に真摯に野球に取り組む姿勢は本場アメリカのファンからも喝采を浴び、「10人目のスターター」としてチームとともに戦う姿勢を見せました。また、野球選手らしからぬ文才にも恵まれ、その著書も高く評価されています。
近い将来、「田口監督」が誕生しそうな予感がします。
背番号6番をつけた選手の傾向とは?
オリックスバファローズの前身球団である、阪急ブレーブスや近鉄バファローズ時代は、主に野手がつけてきた傾向があります。他の球団の場合は、6番をつけた選手は内野手が多いのですが、外野手も多くつけてきたのが特徴です。
そして華やかな選手が少ない印象を受けたのは意外でした。近鉄では、金村選手のイメージが強すぎて賑やかな番号、という印象だったのですが、島田、安井、そして石渡の各選手はバリバリのレギュラーというわけではなく、ここぞという時にチームを救う選手たちでした。
それは阪急にも言えることで、大橋、熊野、田口の各選手はレギュラーでしたが、それ以外の6番を着けた選手は、近鉄の歴史と同じ系譜と言っていいでしょう。
統合後の6番の歴史は、ちょっと形を変えてはいますが、「チームを救う選手の番号」となっていると言えます。なぜなら、トレード補強される選手というのは、チームの弱点を補うべく招かれる選手だからです。
統合前は野手の、統合後は移籍選手の番号というのが、オリックスバファローズの背番号6番の傾向といえます。
⇒オリックスバファローズの話題
他にも野球に関する話題を多数お届けしています。
⇒野球に関する話題はこちらからどうぞ
背番号別の特徴に関しての話題を提供しています。
⇒背番号別の特徴
おわりに
今回は、オリックスバファローズの背番号6番を特集してきましたが、いかがだったでしょうか?
2020年現在で6番をつけている宗選手は、2018年には74試合、2019年は54試合とキャリアを重ねています。まだ24歳と若く、今後が楽しみな選手の一人です。
後藤駿太選手と宗選手の俊足1・2番コンビがかき回し、吉田正尚選手がきっちりチャンスをモノにする。その得点を山岡泰輔投手や山本由伸投手を中心とした先発陣が守り、増井浩俊投手がきっちり締める・・・。
そんなオリックスの必勝パターンは、現実のものとなる日がもうすぐそこまで来ているような気がします。
宗選手の活躍に注目していきたいと思います。
最後までお読みいただき大感謝!みっつでした。