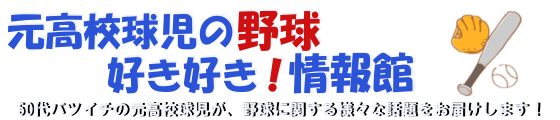こんにちは、当ブログの管理人、元高校球児のみっつです!
東都大学野球連盟は、歴史・実力・人気ともに東京六大学リーグに並ぶ大学野球屈指のリーグです。東京近郊を所在とした21校の大学が加盟しており、4部制でリーグ戦が行われています。
今回は、東都大学野球連盟を特集します。連盟に加盟している全ての学校や優勝経験のある大学、さらに歴代の優勝校や個人記録にも迫りますので、楽しみにしてくださいね。
■目次(クリックすると飛びます)
東都大学野球連盟の全加盟校のご紹介
まずは、東都大学野球連盟の全ての加盟校をご紹介します。
| 大学名 | 連盟加入年 |
|---|---|
| 亜細亜大学 | 1959年 |
| 國學院大学 | 1931年 |
| 駒澤大学 | 1948年 |
| 中央大学 | 1931年 |
| 東洋大学 | 1940年 |
| 立正大学 | 1959年 |
| 青山学院大学 | 1951年 |
| 国士舘大学 | 1959年 |
| 専修大学 | 1925年 |
| 拓殖大学 | 1949年(1951年に脱退、1963年に再加盟) |
| 大正大学 | 1948年 |
| 日本大学 | 1931年 |
| 学習院大学 | 1950年 |
| 芝浦工業大学 | 1951年 |
| 順天堂大学 | 1958年 |
| 上智大学 | 1940年 |
| 成蹊大学 | 1951年 |
| 東京農業大学 | 1931年 |
| 東京工業大学 | 1940年 |
| 一橋大学 | 1936年 |
| 東京都市大学 | 1951年 |
優勝経験のある主な加盟校のご紹介
次に、東都大学野球連盟の加盟校のうちで、1部リーグで優勝経験のある大学をご紹介します。
専修大学
優勝回数 32回
主なOB 中尾孝義、黒田博樹、長谷川勇也、池田駿、高橋礼など
特色
専修大学は、東都大学野球連盟の前身の五大学野球連盟の創設時から加盟している大学です。戦国・東都大学野球リーグで最多となる32回のリーグ優勝を誇ります。
しかし、リーグ優勝のほとんどが昭和期のもので、平成以降は苦戦が続いています。2015年春のリーグ戦では26年ぶりに優勝しましたが、2年後には2部に降格してしまいました。
近年は昇格と降格を繰り返していますが、現在は2部でリーグ戦を戦い、1部昇格を狙います。
過去の栄光が強い印象の大学で、戦前からプロ野球選手を輩出していますが、近年でもソフトバンクで活躍し侍ジャパンにも選出された、高橋礼選手などがプロ入りしています。

駒澤大学
優勝回数 27回
主なOB 中畑清、野村謙二郎、新井貴浩、大島洋平、今永昇太など
特色
駒澤大学は、戦後に創部し東都大学野球連盟に加盟しました。1971年から35年に渡ってチームを率いた太田監督のもとでは、リーグ優勝22回、全日本大学野球選手権優勝6回、明治神宮大会優勝5回と、大学野球界屈指の名門大学となりました。
全国大会の出場回数・成績ともに、駒澤大が東都大学野球連盟でナンバーワンの実績となっています。
その後、神宮大会で優勝した翌年に2部に降格したりと、苦しい戦いも続いておりますがそれも東都大学野球リーグのレベルの高さゆえのことかもしれません。
名門大学なだけあり、昭和期から現在に至るまで多くのプロ野球選手を輩出しており、その中には監督経験者やタイトル獲得者などの名選手がずらりと並んでいます。
中央大学
優勝回数 25回
主なOB 高木豊、阿部慎之助、亀井義行、美馬学、澤村拓一など
中央大学は、連盟創設時から加盟している5つの大学のうちの1つです。リーグ黎明期には専修大や日本大と優勝争いを繰り広げ、リーグ優勝のほとんどが昭和期のものです。
2部降格するなどの低迷期もありましたが、ここ10年以上は1部に定着しています。また、直近に行われた2019年秋のリーグ戦王者でもあります。
歴史のある名門大学なだけあり、挙げきれないほどの名選手をプロ野球界に送り込んできました。ここ10年ほどの間にも、10人以上の選手がプロ野球入りしており、選手の育成に関しては安定しています。
亜細亜大学
優勝回数 26回
主なOB 与田剛、高津臣吾、井端弘和、松田宣浩、山崎康晃など
特色
亜細亜大学は、1958年創部・1959年加盟と、東都大学野球連盟の強豪校の中では歴史の浅い大学です。
平成期では東都を代表する強豪校です。特に、2011年から2014年にかけては、強豪ひしめく東都リーグで6季連続優勝などの輝かしい成績をあげています。
OBにはプロ野球選手も多く、プロの舞台で活躍してきました。高校時代からのスター選手は少ない印象ですが、高校時代に特筆する実績がなくとも亜細亜大名物の厳しい練習が、選手を確かに成長させているのだと感じます。
日本大学
優勝回数 23回
主なOB 佐藤義則、真中満、村田修一、長野久義、京田陽太など
特色
日本大学は、連盟創設時から加盟しており、歴史のある大学です。OBは昭和期から近年に至るまで、数多くの選手がプロ野球界で活躍しています。
連盟創設当初から優勝を争いを繰り広げてきた強豪ですが、たびたび2部に降格しています。2016年秋には23回目のリーグ優勝を果たしましたが、翌年には2部に降格してしまい、現在は2部で1部昇格を目指して戦っています。
全国にある野球の強い付属校や系列校から多くの部員が入部してきており、東都リーグ屈指の部員の多さが特徴的です。
また、日本大学は日本で最大規模の大学で、学部ごとにキャンパスがわかれており、野球部のグラウンドが遠い千葉県習志野市にあるなどの部分は、部活動を行う上でネックの部分かもしれません。
東洋大学
優勝回数 20回
主なOB 達川光男、今岡誠、清田育宏、鈴木大地、梅津晃大など
特色
東洋大学は、現在の東都リーグを代表する強豪です。強豪のイメージが強い東洋大ですが、1940年に加盟してから、初優勝まで36年かかりました。
これまで20回の優勝がありますが、半分以上がここ15年以内のものであり、特に近年の強さが際立ちます。この間、2部降格などの時期もありましたが、少しも気を抜けない東都リーグのレベルの高さならではです。
部員も甲子園優勝投手など、全国の強豪校の主力級の選手が入部しており、その層の厚さは、レベルの高い東都リーグの中でも随一です。
東洋大学からも多くの選手がプロ野球界で活躍してきました。中でも2018年には、上茶谷選手・甲斐野選手・梅津選手・中川選手の同学年の4人がドラフト指名され話題となりました。
青山学院大学
優勝回数 12回
主なOB 小久保裕紀、川越英隆、井口資仁、石川雅規、吉田正尚など
特色
青山学院大学野球部の歴史は、1883年(明治16年)からスタートしており、大学野球界においても屈指の歴史を誇ります。1972年に初の1部昇格を果たすと、1988年のリーグ初優勝からの20年の間に12回リーグ優勝をしており、一気に強豪校として定着しました。
小久保裕紀選手や井口資仁選手などの、後のプロ野球界のスター選手も在籍してきました。また、全日本大学野球選手権には5度出場し、4度の優勝と1度の準優勝と輝かしい成績をあげています。
2014年に2部に降格してからは、なかなか1部に昇格できずにいますが、吉田正尚選手などもプロ野球界に送り込んできました。
最近では監督が度々交代し、それに伴い部員が退部するなど、本来の強さは見せつけることはできていませんが、6年ぶりの1部復帰を狙っています。
芝浦工業大学
優勝回数 3回
主なOB 岩下光一、片岡新之介、河村健一郎、伊原春樹、道原裕幸など
特色
芝浦工業大学は、工業系の私立大学ですが、東都リーグでは過去に3度の優勝があります。優勝回数の上位陣は、日本でも有数の規模の総合大学ばかりなので、芝浦工業大学のような存在は珍しいものとなりつつあります。
東都大学野球連盟には1951年(昭和26年)に加盟すると、1957年に1部に昇格しました。スポーツ推薦制度により有力な選手が入学し始めたことで、昭和30年代から昭和40年代なかばにかけて、東都リーグの1部でも強豪としてリーグを盛り上げました。
その後、学園紛争などの影響もあり、スポーツ推薦制度が撤廃されると、部員数も少なくなり衰退の一途を辿ってしまいます。1973年には2部に、1976年には3部まで降格してしまい、現在まで3部より上に上がることはできていません。
野球部に対する学校側の力の入れ具合や新興校の躍進により、かつての強豪が苦戦を強いられるのは、どこのリーグでも共通のようです。
立正大学
優勝回数 2回
主なOB 西口文也、武田勝、黒木優太、伊藤裕季也、小郷裕哉など
特色
立正大学は、リーグ優勝はまだ2回ですが、東都リーグにおける新鋭校の筆頭と言っていいかもしれません。
1959年に連盟に加盟すると、長年2部どまりでしたが、1993年に初めて1部に昇格します。その後、1部と2部を行ったり来たりしますが、2009年に悲願の1部リーグ優勝を果たすと、勢いそのままに明治神宮大会でも優勝し、一気に全国でも強豪の仲間入りをしました。
翌2010年には2部に降格してしまいますが、ようやく2017年に1部復帰すると、2018年秋季リーグで優勝し、またもや明治神宮大会で優勝します。
ここ数年、毎年のようにプロ野球選手を輩出しており、東都リーグでは近年最も注目度を挙げた大学です。
今後もリーグ戦や全国大会でのタイトルが増えそうです。
國學院大学
優勝回数 2回
主なOB 渡辺俊介、嶋基宏、聖澤諒、杉浦稔大、清水昇など
特色
國學院大学は、連盟創設に携わった5つの大学のうちの1つです。前身の五大学野球連盟時には、同率優勝をしていますが、記録上は「優勝預かり」となっており、優勝回数にはカウントされていません。
リーグが2部制を開始すると、すぐさま2部に降格してしまい、長年、2部リーグが主戦場となってしまいます。
國學院大のOBであり、東北高校や仙台育英高校を率いた高校野球の名将の竹田監督が就任すると、徐々にではありますがチーム力が増し、2006年に1部昇格を果たしました。
その後、入れ替えの激しい東都リーグですので、2部に降格することもありましたが、充分、1部に定着していると言っても過言ではありません。また、2010年には悲願の1部リーグ初優勝を遂げ、2021年春のリーグ戦でも優勝しています。
大学がスポーツに力を入れ始めたこともあり、2000年代以降は甲子園経験者が多数入部しており、チーム力が増しています。
国士舘大学
優勝回数 1回
主なOB 古城茂幸、小松聖、岩崎優、椎野新、高部瑛斗など
特色
国士舘大学には、体育学部があり、学生アスリートや体育教師を目指す学生が多く在籍しており、各種学生スポーツに力を入れている大学です。
野球部に置いては、1959年に東都大学野球連盟に加盟し、1974年に初の1部昇格を果たします。1979年秋には1部リーグで初優勝をしますが、翌年には2部に降格していまいました。
その後、1部に度々昇格していますが、定着することはできずに2部に降格しています。2部においても、リーグ最下位であやうく3部降格となりかけるシーズンも度々ありますが、入替戦では勝利しており、なんとか降格は免れています。
そんな中でも定期的にプロ野球選手を輩出しており、2019年に千葉ロッテの高部選手は、1部での試合経験はありませんが、2部での実績が認められてドラフト3位で指名を受けています。
学習院大学
優勝回数 1回
特色
学習院大学の野球部の歴史は、1889年に発足したベースボール同好会を端初としており、大学野球界の中においても、屈指の歴史を誇ります。昭和20年代なかばから昭和30年代なかばの約10年ほど東都リーグの1部に在籍し、1958年には唯一の1部優勝があります。
1961年に2部に降格し、1982年に3部に降格すると、その後2部への復帰はありません。
学習院大もそうですが、東京農業大や芝浦工業大などのかつて1部リーグで戦った大学でも、3部まで降格してしまうのは、往年のファンにとっては寂しいものかもしれません。
それでも、2017年には3部で優勝し、2戦先勝の2部入替戦では、1戦目に勝ち、2戦目は逆転負け、3戦目も延長戦にもつれこむ接戦でしたが逆転負けし、35年ぶりの2部復帰は叶いませんでした。
スポーツ推薦はないのですが、3部では常に上位に位置し、入替戦では2部の大学をおびやかしています。
東都大学野球連盟の歴代優勝校のご紹介
東都大学野球連盟の1部リーグ戦の歴代優勝校について、前身となる五大学野球連盟がリーグ戦を開始した1931年のものからご紹介します。
| 年度(西暦) | 年度(和暦) | 春の優勝校 | 秋の優勝校 |
|---|---|---|---|
| 1931年 | 昭和6年 | 専修大 | (日本大・國學院大) |
| 1932年 | 昭和7年 | 中央大 | (中央大・日本大) |
| 1933年 | 昭和8年 | 専修大 | 日本大 |
| 1934年 | 昭和9年 | 専修大 | 中央大 |
| 1935年 | 昭和10年 | 専修大 | 専修大 |
| 1936年 | 昭和11年 | 専修大 | 中央大 |
| 1937年 | 昭和12年 | 中央大 | 中央大 |
| 1938年 | 昭和13年 | 日本大 | 中央大 |
| 1939年 | 昭和14年 | 専修大 | 専修大・中央大・日本大 |
| 1940年 | 昭和15年 | 専修大 | 専修大 |
| 1941年 | 昭和16年 | 専修大 | 専修大 |
| 1942年 | 昭和17年 | 中央大 | 専修大 |
| 1946年 | 昭和21年 | 専修大 | 中央大 |
| 1947年 | 昭和22年 | 中央大 | 専修大 |
| 1948年 | 昭和23年 | 中央大 | 中央大 |
| 1949年 | 昭和24年 | 日本大 | 中央大 |
| 1950年 | 昭和25年 | 専修大 | 日本大 |
| 1951年 | 昭和26年 | 専修大 | 専修大 |
| 1952年 | 昭和27年 | 専修大 | 日本大 |
| 1953年 | 昭和28年 | 中央大 | 日本大 |
| 1954年 | 昭和29年 | 専修大 | 日本大 |
| 1955年 | 昭和30年 | 日本大 | 専修大 |
| 1956年 | 昭和31年 | 日本大 | 日本大 |
| 1957年 | 昭和32年 | 専修大 | 専修大 |
| 1958年 | 昭和33年 | 中央大 | 学習院大 |
| 1959年 | 昭和34年 | 専修大 | 日本大 |
| 1960年 | 昭和35年 | 日本大 | 専修大 |
| 1961年 | 昭和36年 | 日本大 | 芝浦工業大 |
| 1962年 | 昭和37年 | 駒澤大 | 日本大 |
| 1963年 | 昭和38年 | 駒澤大 | 中央大 |
| 1964年 | 昭和39年 | 駒澤大 | 中央大 |
| 1965年 | 昭和40年 | 専修大 | 専修大 |
| 1966年 | 昭和41年 | 日本大 | 亜細亜大 |
| 1967年 | 昭和42年 | 中央大 | 亜細亜大 |
| 1968年 | 昭和43年 | 駒澤大 | 芝浦工業大 |
| 1969年 | 昭和44年 | 日本大 | 日本大 |
| 1970年 | 昭和45年 | 芝浦工業大 | 中央大 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亜細亜大 | 日本大 |
| 1972年 | 昭和47年 | 中央大 | 駒澤大 |
| 1973年 | 昭和48年 | 中央大 | 駒澤大 |
| 1974年 | 昭和49年 | 駒澤大 | 中央大 |
| 1975年 | 昭和50年 | 駒澤大 | 駒澤大 |
| 1976年 | 昭和51年 | 駒澤大 | 東洋大 |
| 1977年 | 昭和52年 | 駒澤大 | 駒澤大 |
| 1978年 | 昭和53年 | 専修大 | 東洋大 |
| 1979年 | 昭和54年 | 中央大 | 国士舘大 |
| 1980年 | 昭和55年 | 駒澤大 | 亜細亜大 |
| 1981年 | 昭和56年 | 亜細亜大 | 専修大 |
| 1982年 | 昭和57年 | 東洋大 | 専修大 |
| 1983年 | 昭和58年 | 駒澤大 | 駒澤大 |
| 1984年 | 昭和59年 | 亜細亜大 | 駒澤大 |
| 1985年 | 昭和60年 | 東洋大 | 駒澤大 |
| 1986年 | 昭和61年 | 東洋大 | 駒澤大 |
| 1987年 | 昭和62年 | 駒澤大 | 東洋大 |
| 1988年 | 昭和63年 | 駒澤大 | 青山学院大 |
| 1989年 | 平成元年 | 専修大 | 青山学院大 |
| 1990年 | 平成2年 | 亜細亜大 | 亜細亜大 |
| 1991年 | 平成3年 | 東洋大 | 駒澤大 |
| 1992年 | 平成4年 | 駒澤大 | 日本大 |
| 1993年 | 平成5年 | 青山学院大 | 駒澤大 |
| 1994年 | 平成6年 | 駒澤大 | 青山学院大 |
| 1995年 | 平成7年 | 東洋大 | 青山学院大 |
| 1996年 | 平成8年 | 青山学院大 | 亜細亜大 |
| 1997年 | 平成9年 | 亜細亜大 | 駒澤大 |
| 1998年 | 平成10年 | 亜細亜大 | 亜細亜大 |
| 1999年 | 平成11年 | 青山学院大 | 青山学院大 |
| 2000年 | 平成12年 | 亜細亜大 | 東洋大 |
| 2001年 | 平成13年 | 日本大 | 駒澤大 |
| 2002年 | 平成14年 | 亜細亜大 | 亜細亜大 |
| 2003年 | 平成15年 | 亜細亜大 | 青山学院大 |
| 2004年 | 平成16年 | 日本大 | 中央大 |
| 2005年 | 平成17年 | 青山学院大 | 青山学院大 |
| 2006年 | 平成18年 | 青山学院大 | 亜細亜大 |
| 2007年 | 平成19年 | 東洋大 | 東洋大 |
| 2008年 | 平成20年 | 東洋大 | 東洋大 |
| 2009年 | 平成21年 | 東洋大 | 立正大 |
| 2010年 | 平成22年 | 東洋大 | 國學院大 |
| 2011年 | 平成23年 | 東洋大 | 亜細亜大 |
| 2012年 | 平成24年 | 亜細亜大 | 亜細亜大 |
| 2013年 | 平成25年 | 亜細亜大 | 亜細亜大 |
| 2014年 | 平成26年 | 亜細亜大 | 駒澤大 |
| 2015年 | 平成27年 | 専修大 | 亜細亜大 |
| 2016年 | 平成28年 | 亜細亜大 | 日本大 |
| 2017年 | 平成29年 | 東洋大 | 東洋大 |
| 2018年 | 平成30年 | 東洋大 | 立正大 |
| 2019年 | 令和元年 | 東洋大 | 中央大 |
| 2020年 | 令和2年 | コロナウイルスの影響により中止 | 亜細亜大学 |
| 2021年 | 令和3年 | 國學院大學 | |
| ※昭和6年秋、昭和7年秋は優勝預かり | |||
| ※昭和14年秋は3校同時優勝 |
学校別優勝回数ランキング
続いて、学校別にリーグ戦の優勝回数とランキングを紹介します。
| 順位 | 学校名 | 優勝回数(春・秋) |
|---|---|---|
| 1位 | 専修大学 | 32回(19・13) |
| 2位 | 駒澤大学 | 27回(14・13) |
| 3位 | 中央大学 | 25回(11・14) |
| 3位 | 亜細亜大学 | 26回(13・13) |
| 5位 | 日本大学 | 23回(10・13) |
| 6位 | 東洋大学 | 20回(13・7) |
| 7位 | 青山学院大学 | 12回(5・7) |
| 8位 | 芝浦工業大学 | 3回(1・2) |
| 9位 | 立正大学 | 2回(0・2) |
| 10位 | 國學院大学 | 2回(1・1) |
| 10位 | 国士舘大学 | 1回(0・1) |
| 10位 | 学習院大学 | 1回(0・1) |
優勝回数は、専修大が32回で最多ですが、飛び抜けて優勝回数が多い大学はありません。
歴代の個人記録のご紹介
東都大学野球連盟の各種個人記録について、打撃部門と投手部門に分けてご紹介します。
打撃部門
打撃部門では、通算の安打や本塁打、盗塁数、1季における最高打率、最多安打・本塁打
通算安打
1位 藤波行雄選手(中央大) 133安打 1970年~1973年
2位 高木豊選手(中央大) 115安打 1977年~1980年
3位 石毛宏典選手(駒澤大) 114安打 1975年~1978年
通算本塁打
1位 井口資仁選手(青山学院大) 24本 1993年~1996年
2位タイ 大橋穣選手(亜細亜大) 20本 1965年~1968年
2位タイ 村田修一選手(日本大) 20本 1999年~2002年
通算盗塁数
1位 野村謙二郎選手(駒澤大学) 52盗塁 1985年~1988年
1季最高打率
1位 加藤正二選手(中央大) .577(26打数15安打) 1937年秋
2位 鈴木望選手(駒澤大) .576(33打数19安打) 1987年春
3位 横山政之選手(専修大) .571(21打数12安打) 1959年春
1季最多安打
1位 林弘典選手(日本大) 30安打 2001年春
1季最多本塁打
1位 井口資仁選手(青山学院大) 8本塁打 1994年秋
1位 村田修一選手(日本大) 8本塁打 2001年秋
投手部門
投手部門では、通算の勝利と奪三振、1季での最多奪三振をご紹介します。
通算勝利
1位 芝池博明選手(専修大) 41勝31敗 1965年~1968年
2位タイ 田村政雄選手(中央大) 39勝33敗 1972年~1975年
2位タイ 松沼雅之選手(東洋大) 39勝26敗 1975年~1978年
通算奪三振
1位 東浜巨選手(亜細亜大) 420個 2009年~2012年平
2位 大場翔太選手(東洋大) 410個 2004年~2007年
3位 小池秀郎選手(亜細亜大) 394個 1987年~1990年
1季最多奪三振
1位 大場翔太選手(東洋大) 115個 2007年春
2位 小池秀郎選手(亜細亜大) 111個 1990年春
3位 大場翔太選手(東洋大) 101個 2007年秋
⇒全日本大学野球選手権!歴代の優勝校や優勝回数ランキング・出場資格をご紹介
⇒明治神宮野球大会!大学の出場条件と歴代優勝校をご紹介!
最後までお読みいただき大感謝!みっつでした。