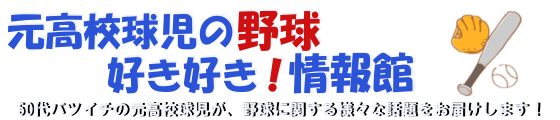こんにちは、当ブログの管理人、元高校球児のみっつです!
東京新大学野球連盟は、その名のとおり、東京近郊に所在を置く大学により構成される連盟です。新設大学の加盟を積極的に受け入れており、2021年現在では、関東では最多の23校による4部制でリーグ戦が行われています。
今回は、そんな東京新大学野球連盟を特集します。加盟している全大学や優勝経験のある大学、さらに歴代優勝校や個人記録にも触れますので、楽しみにしてくださいね。
■目次(クリックすると飛びます)
東京新大学野球連盟の全加盟校のご紹介
まずは、東京新大学野球連盟に加入している23校全てをご紹介します。
共栄大学
・連盟加入年 2003年
流通経済大学
・連盟加入年 1977年
駿河台大学
・連盟加入年 1992年
東京国際大学
・連盟加入年 1985年
創価大学
・連盟加入年 1974年
杏林大学
・連盟加入年 1987年
東京学芸大学
・連盟加入年 1958年
東京都立大
・連盟加入年 1958年
東洋学園大学
・連盟加入年 2012年
高千穂大学
・連盟加入年 1958年
日本大学生物資源科学部
・連盟加入年 1958年
工学院大学
・連盟加入年 1958年
淑徳大学埼玉キャンパス
・連盟加入年 2003年
東京外国語大学
・連盟加入年 1958年
日本工業大学
・連盟加入年 1969年
東京理科大学
・連盟加入年 1958年
文京学院大学
・連盟加入年 2006年
東京農工大学
・連盟加入年 1958年
電気通信大学
・連盟加入年 1958年
東京工科大学
・連盟加入年 2002年
国際基督教大学
・連盟加入年 1977年
東京電機大学
・連盟加入年 1958年
東京海洋大学
・連盟加入年 2004年
優勝経験のある加盟校のご紹介
続いて、東京新大学野球連盟に加盟している大学の中から、1部リーグで優勝経験のある大学についてご紹介します。
創価大学
・優勝回数 47回
・主なOB 小谷野栄一、小川泰弘、倉本寿彦、石川柊太、田中正義など
特色
創価大学は1970年代の連盟加盟と、後発組ながら連盟最多となるリーグ優勝を誇ります。ここ30年ほどで40回以上もリーグ優勝しており、昨年まで27年連続で春か秋に優勝しておりその安定感が際立ちます。
2000年代にはリーグ戦43連勝を記録するなど、現在では1強体制を築いていると言っても過言ではありません。その成績のおかげか、プロ野球選手も20名以上輩出しており、ノーヒットノーランの小川選手やドラフトで5球団強豪の田中選手などOBの質量ともに連盟随一です。
野球部ではセレクションが行われているため部員は80名程度ですが、全国の強豪校出身の選手がズラリと並んでいます。
また、専用球場にはクラブハウスや室内練習場に加え、最新の寮まで完備しており、充実の環境でレベルの高い練習ができています。
流通経済大学
・優勝回数 30回
・主なOB 高橋信夫、加藤竜人、井川翔、神戸拓光、生田目翼など
特色
流通経済大学は、茨城県龍ヶ崎市と千葉県松戸市にキャンパスを置く大学です。サッカー部が全国的な強豪として知られる大学ですが、野球部も連盟で2位となる30回のリーグ優勝がある強豪です。
創部と連盟加盟は創価大学よりも後の1977年ですが、その全盛期は1980年代~1990年代と創価大学よりも早くリーグ7連覇やリーグ9連覇などの栄光もありました。
現在も安定してリーグ上位につけ、ときおり創価大のリーグ連覇を阻んでいます。
また、全日本大学野球選手権と明治神宮大会では準優勝の経験があり、東京新大学野球連盟の大学としてはともに最高成績となっています。
部員は甲子園常連校の選手はあまりいませんが、関東の強豪高校出身の選手が多めです。大学の設立母体が、社会人野球でも強豪の日本通運ですので、チームの主力選手は日本通運に就職するケースが多いのが特徴的です。
現在は4年生がほとんど引退しているため、下級生中心の若いチームで秋のリーグ戦で優勝を目指します。
東京学芸大学
・優勝回数 17回
・主なOB 栗山英樹、加藤武治
特色
東京学芸大学は、東京都小金井市に所在を置く教員養成の学部を中心とした国立大学です。
前身の東京都新制大学野球連盟時代から優勝経験があり、現在の東京新大学野球連盟となってからも、国立大学ながら首都圏の大学野球連盟としては、かなり多めの17回のリーグ優勝を果たしています。
しかし、そのほとんどが昭和期のもので、平成以降は1度の優勝のみです。長年、日本ハムファイターズを率いた栗山英樹監督は、創価高校出身ながら、教員を目指して東京学芸大学に入学し、リーグ戦で大活躍しました。
しかし、野球への夢が再燃し、ドラフト外でヤクルトスワローズに入団したという珍しい経歴を持っています。
優勝はしていなくともリーグ戦では健闘と言っていい成績を残し続けてきましたが、時代の流れか2010年ごろからは最下位争いをしています。
工学院大学
・優勝回数 8回
特色
工学院大学は、1887年創立の工手学校をルーツとし、日本で最も古い私立の工業系の実業学校です。確認できた野球部の歴史は1949年以降となりますが、前身時代も含めるともっと長い歴史がありそうです。
連盟発足時から加盟している大学の1つで、リーグ戦では8度の優勝経験があります。その全盛時代は、昭和30年代~40年代にかけてで、リーグ優勝は全てこの時期のものです。
それ以降は1978年を最後に1部リーグから遠ざかっており、現在は2部と3部を往復しているのが現状となっています。
40名ほどの部員には、甲子園で見慣れた高校出身の選手もちらほらといますが、野球をしに入学したというよりは勉強をしに入学した選手が多いようです。
学年によってキャンパスが八王子と新宿に別れるため、集まっての練習も難しい部分があるかもしれませんが、付属高校と共用ではありますが、ナイター設備のある前面人工芝のグラウンドで練習を行えているようです。
東京電機大学
・優勝回数 4回
特色
東京電機大学は、連盟発足時から加盟している大学の1つです。加盟当初から1部と2部を行ったり来たりしておりましたが、戦力が充実した年は上位に食い込み1部リーグでも昭和30年代~40年代に4度の優勝があります。
現在は3部リーグと4部リーグを頻繁に往復していますが、4部リーグが主戦場となっています。
4部リーグは昨年はコロナウイルスの影響でリーグ戦が春秋とも中止になってしまいました。2年ぶりに開催された2021年春のリーグ戦でも1勝3敗で最下位に終わるなど、全盛期の姿は見る影もありません。
部員数も少なく10数人と、1チームを作るのがやっとのようです。大学としても野球に力を入れているという感じではなさそうです。
大学のほとんどの学部がある千住キャンパスには野球で使用できるグラウンドが無く、練習環境もなかなか整っていないのかもしれません。
高千穂大学
・優勝回数 4回
・主なOB 戸田亮、三ツ間卓也
特色
高千穂大学は、東京都杉並区にキャンパスを置く商業系の大学です。
野球部は今年、創部90周年のようで、記録が残る中では東京新大学野球連盟加盟校で最も古い歴史のある野球部です。成績の方では、高千穂商科大時代の昭和50年代前半に4度のリーグ優勝経験があります。
長年1部リーグを盛り上げてきましたが、ここ5年ほどは2部リーグから昇格できていません。
中日ドラゴンズに入団した三ツ間選手は、大学時代のほとんどが2部リーグ止まりでプロのスカウトの目に留まることはありませんでした。内定していた就職先を辞退し独立リーグのトライアウトを受験した結果、見事に武蔵ヒートベアーズから指名を受けています。
さらに、1年で育成ドラフトで中日ドラゴンズに入団すると、1シーズンで支配下登録を勝ち取りました。2部リーグなどで注目を集められない中でもプロを目指す選手にとっては、とても良いモデルケースのように思います。
共栄大学
・優勝回数 4回
特色
共栄大学は、埼玉県春日部市に所在を置く東京新大学野球連盟で最も勢いのある大学です。もともとは女学校だった経緯があるため、野球部の創部は2002年と歴史は20年余りです。また、高校野球の強豪校である春日部共栄高校は、共栄大学の併設校となっています。
2003年に連盟加盟すると、4部から順調に1部への階段を駆け上がりました。2006年の1部昇格以降はしばらく足踏みが続いていましたが、2016年に初優勝を成し遂げると、ここ5年で4度優勝しています。
部員はそこまで強豪校出身の選手が多いわけではありませんが、セレクションがありながら100人を超える大所帯となっており、ベンチ入りメンバーやレギュラー争いは激しいものとなっています。
リーグの強豪校の仲間入りをした共栄大学ですが、これまでプロ野球選手が生まれていません。今後に期待がかかります。
東京海洋大学
・優勝回数 3回(東京水産大2回と東京商船大1回の合計)
特色
東京海洋大学は、東京商船大学と東京水産大学が統合し、2003年に設置された国立大学です。東京商船大学と東京水産大学の両校ともに、1部リーグでの優勝経験があります。
しかし、両校とも1975年ごろを最後に1部リーグから遠ざかっており、2003年には水産大が3部、商船大が4部に所属しており、統合の際には、水産大が所属していた3部リーグへの所属となりました。
部員の中には実力のある高校出身の選手もちらほらおりますが、大学の性質上、勉学が優先となってしまうのは仕方がありません。
2009年に4部リーグに降格して以降、昇格はおろか、4部での優勝すらできていない状況が続いています。当面の目標は4部での優勝、そして入替戦に勝利しての3部昇格ということになりそうです。
また、新入部員の確保にも苦戦しているようなので、歴史のある野球部にはぜひ存続して欲しいところです。
日本大学生物資源科学部
・優勝回数 2回
特色
日本大学生物資源科学部は、神奈川県藤沢市にキャンパスがあります。
日本大学は学部ごとに東京近郊に多くのキャンパスがありますが、この生物資源科学部と南東北大学リーグの工学部と千葉県大学リーグの生産工学部、東海地区大学リーグの国際関係学部の4つの学部はそれぞれ独立して各リーグに所属しています。
日本大学と言えば各学部に付属高校として併設校が設置されていることが多いのですが、生物資源科学部には日大藤沢高校が併設されています。また、西東京の強豪の日大鶴ケ丘も、生物資源科学部の前身となった農獣医学部の併設校として設置されました。
生物資源科学部野球部は単独学部でのリーグ戦参戦ながら、昭和40年代に2度のリーグ優勝経験があります。現在は2部リーグが主戦場となっており、ここ数年は2部リーグでも低迷が続いています。
まずは20年以上遠ざかっている1部復帰を目指します。
東京都立大学
・優勝回数 2回
特色
東京都立大は、東京新大学野球連盟の母体の1つとなった理工科系リーグ時代からリーグ戦に参戦しており、国公立大学としては歴史がある野球部です。
旧東京都立大時代には、昭和30年代に2度のリーグ優勝経験があります。その後、都立大のほか都立科学技術大と都立保健科学大と都立短大の4校を母体として、2005年に首都大学東京が設置されました。
その首都大は、メインキャンパスが都立大のものを使用していたことなどから、戦績等は都立大のものを引き継いでいます。
公立大ということで、戦力の確保や部の強化といった部分では強豪私立大には差をつけられていますが、長年2部リーグをキープしており、ときおり昇格までは行かないまでも、1部との入替戦にも進出しています。
2020年には首都大学東京から、現在の東京都立大に校名が変更されましたが、そのきっかけの1つとしては首都大への認知度の低さが挙げられています。認知度アップで野球部も一皮むけるのか注目したいです。
日本工業大学
・優勝回数 1回
特色
日本工業大学は、埼玉県宮代町などにキャンパスを置く大学です。1969年の連盟加盟後は、順調に1部まで昇格し、1976年秋には1部リーグ優勝を成し遂げました。
しかし、目立った成績はその優勝1回のみといったところで、1部リーグに在籍していた期間も短いため、強豪としては認知されていません。
現在は3部リーグがメインで、2部昇格を狙う勢力の1つとしてリーグ戦に臨んでいます。
野球部の硬式ホームページを見てみると、上のステージや教職員として指導者を目指す選手へのサポートに力を入れているようです。また、社会勉強のために部員にはアルバイトを推奨しているのも他の野球部にはない面白いところです。
現在の部員は20名ほどですが、近年には独立リーグに進んだ選手もいます。野球をする上での環境は重要ですが、1番は本人の意識や努力が重要だということを再認識させられます。
東京国際大学
・優勝回数 1回
・主なOB 伊藤和雄
特色
東京国際大学は埼玉県川越市や新宿区にキャンパスを置く大学です。国際商科大学時代の1985年に連盟に加盟し、翌年には東京国際大学へ名称を変更しました。
順調に1部まで昇格したものの、しばらく足踏みが続いたような感じでしたが2011年春に初めて1部リーグで優勝しました。優勝はこの1回のみですが、現在も1部で優勝を狙う一角として戦いを繰り広げています。
当然入部前にはセレクションがありますが、それでも部員は200人に近い大所帯となっており、レギュラー争いに関してはリーグで最も激しいものかもしれません。
大学としても各種運動部の活動にかなり力を入るだけでなく、都心に大型のキャンパスを建設中で、ノリに乗っている感じがします。
野球部も間違いなく、リーグ優勝回数伸ばしていったり、プロ野球選手も輩出していくようになることが予想されます。
歴代優勝校のご紹介
東京新大学野球連盟のリーグ戦の歴代優勝校について、リーグ戦が開始された1958年のものからご紹介します。
| 年度(西暦) | 年度(和暦) | 春の優勝校 | 秋の優勝校 |
|---|---|---|---|
| 1958年 | 昭和33年 | 東京経済大 | 東京学芸大 |
| 1959年 | 昭和34年 | 東京学芸大 | 東京都立大 |
| 1960年 | 昭和35年 | 東京学芸大 | 東京電機大 |
| 1961年 | 昭和36年 | 東京電機大 | 東京学芸大 |
| 1962年 | 昭和37年 | 工学院大 | 東京都立大 |
| 1963年 | 昭和38年 | 工学院大 | 東京水産大 |
| 1964年 | 昭和39年 | 工学院大 | 工学院大 |
| 1965年 | 昭和40年 | 東京水産大 | 東京学芸大 |
| 1966年 | 昭和41年 | 工学院大 | 工学院大 |
| 1967年 | 昭和42年 | 工学院大 | 不明 |
| 1968年 | 昭和43年 | 工学院大 | 不明 |
| 1969年 | 昭和44年 | 東京商船大 | 東京学芸大 |
| 1970年 | 昭和45年 | 東京学芸大 | 日大農獣医学部 |
| 1971年 | 昭和46年 | 東京電機大 | 東京学芸大 |
| 1972年 | 昭和47年 | 東京学芸大 | 日大農獣医学部 |
| 1973年 | 昭和48年 | 東京学芸大 | 東京学芸大 |
| 1974年 | 昭和49年 | 東京学芸大 | 東京電機大 |
| 1975年 | 昭和50年 | 高千穂商科大 | 東京学芸大 |
| 1976年 | 昭和51年 | 東京学芸大 | 日本工業大 |
| 1977年 | 昭和52年 | 創価大 | 高千穂商科大 |
| 1978年 | 昭和53年 | 高千穂商科大 | 高千穂商科大 |
| 1979年 | 昭和54年 | 流通経済大 | 流通経済大 |
| 1980年 | 昭和55年 | 東京学芸大 | 流通経済大 |
| 1981年 | 昭和56年 | 東京学芸大 | 流通経済大 |
| 1982年 | 昭和57年 | 流通経済大 | 流通経済大 |
| 1983年 | 昭和58年 | 流通経済大 | 流通経済大 |
| 1984年 | 昭和59年 | 流通経済大 | 流通経済大 |
| 1985年 | 昭和60年 | 創価大 | 流通経済大 |
| 1986年 | 昭和61年 | 流通経済大 | 流通経済大 |
| 1987年 | 昭和62年 | 流通経済大 | 流通経済大 |
| 1988年 | 昭和63年 | 流通経済大 | 流通経済大 |
| 1989年 | 平成元年 | 流通経済大 | 流通経済大 |
| 1990年 | 平成2年 | 創価大 | 創価大 |
| 1991年 | 平成3年 | 東京学芸大 | 流通経済大 |
| 1992年 | 平成4年 | 創価大 | 流通経済大 |
| 1993年 | 平成5年 | 流通経済大 | 流通経済大 |
| 1994年 | 平成6年 | 創価大 | 創価大 |
| 1995年 | 平成7年 | 創価大 | 創価大 |
| 1996年 | 平成8年 | 創価大 | 創価大 |
| 1997年 | 平成9年 | 創価大 | 創価大 |
| 1998年 | 平成10年 | 流通経済大 | 創価大 |
| 1999年 | 平成11年 | 流通経済大 | 創価大 |
| 2000年 | 平成12年 | 創価大 | 創価大 |
| 2001年 | 平成13年 | 創価大 | 流経大 |
| 2002年 | 平成14年 | 創価大 | 創価大 |
| 2003年 | 平成15年 | 流通経済大 | 創価大 |
| 2004年 | 平成16年 | 創価大 | 創価大 |
| 2005年 | 平成17年 | 創価大 | 創価大 |
| 2006年 | 平成18年 | 創価大 | 創価大 |
| 2007年 | 平成19年 | 創価大 | 流通経済大 |
| 2008年 | 平成20年 | 創価大 | 創価大 |
| 2009年 | 平成21年 | 創価大 | 創価大 |
| 2010年 | 平成22年 | 創価大 | 創価大 |
| 2011年 | 平成23年 | 東京国際大 | 創価大 |
| 2012年 | 平成24年 | 創価大 | 創価大 |
| 2013年 | 平成25年 | 創価大 | 創価大 |
| 2014年 | 平成26年 | 創価大 | 創価大 |
| 2015年 | 平成27年 | 流通経済大 | 創価大 |
| 2016年 | 平成28年 | 共栄大 | 創価大 |
| 2017年 | 平成29年 | 共栄大 | 創価大 |
| 2018年 | 平成30年 | 創価大 | 流通経済大 |
| 2019年 | 令和元年 | 創価大 | 共栄大 |
| 2020年 | 令和2年 | 新型コロナの影響で中止 | 創価大 |
| 2021年 | 令和3年 | 共栄大 |
学校別優勝回数ランキング
続いて、学校別にリーグ戦の優勝回数とそのランキングを紹介します。
| 順位 | 学校名 | 優勝回数(春・秋) |
|---|---|---|
| 1位 | 創価大 | 47回(23・24) |
| 2位 | 流通経済大 | 30回(13・17) |
| 3位 | 東京学芸大 | 17回(10・7) |
| 4位 | 工学院大〇 | 8回(6・2) |
| 5位 | 東京電機大 | 4回(2・2) |
| 5位 | 高千穂大 | 4回(1・3) |
| 5位 | 共栄大 | 4回(3・1) |
| 8位 | 日大生物資源科学部 | 2回(0・2) |
| 8位 | 東京都立大 | 2回(0・2) |
| 8位 | 東京水産大※〇 | 2回(1・1) |
| 11位 | 日本工業大 | 1回(0・1) |
| 11位 | 東京経済大● | 1回(1・0) |
| 11位 | 東京商船大※〇 | 1回(1・0) |
| 11位 | 東京国際大 | 1回(1・0) |
| ※統合し、現在は東京海洋大学 | ||
| 〇優勝回数は判明分のみ | ||
| ●連盟脱退済み |
優勝回数は創価大学が他を引き離していますが、連盟を脱退した大学も含めて優勝経験校が14校もあり、過去と現在で戦力の移り変わりが大きく、混戦模様のリーグと言えます。
歴代の個人記録のご紹介
東京新大学野球連盟の各種個人記録について、打撃部門と投手部門に分けてご紹介します。
打撃部門
通算打率(200打席以上)
1位 吉田勉選手(創価大) 0.395 1988年~1991年
2位 安斉賢治選手(創価大) 0.391 1985年~1988年
3位 栗山英樹(東京学芸大) 0.389 1980年~1983年
シーズン最高打率
1位 熊丸武志選手(創価大) 0.600 2005年春
シーズン最多打点
1位 栗山英樹選手(東京学芸大) 20打点 1982年春
1位 高橋光一(創価大) 20打点 2003年秋
1位 北川利生選手(創価大) 20打点 2015年春
シーズン最多本塁打
1位 濱幸一選手(創価大) 5本 1998年秋
1位 絵鳩隆雄(創価大) 5本 2002年秋
1位 松島圭祐(流通経済大) 5本 2010年秋
投手部門
通算勝利
1位 大塚豊選手(創価大) 41勝 2006年~2009年
通算防御率
1位 松山暢浩選手(創価大) 0.81 1989年~1992年
シーズン最多勝利
1位 佐藤清昌選手(工学院大) 8勝 1963年春
1位 堀田守選手(高千穂大) 8勝 1979年春
1位 小倉丞太郎選手(東京学芸大) 8勝 1998年春
1位 大田悦生選手(流通経済大) 8勝 2001年春
1位 市田勝宏選手(流通経済大) 8勝 2007年秋
1位 奥川裕幸選手(流通経済大) 8勝 2010年秋
1位 小川泰弘選手(創価大) 8勝 2011年秋
シーズン最優秀防御率
1位 田中正義選手(創価大) 0.00 2015年秋
完全試合
南都要選手(創価大) 1978年春
⇒全日本大学野球選手権!歴代の優勝校や優勝回数ランキング・出場資格をご紹介
⇒明治神宮野球大会!大学の出場条件と歴代優勝校をご紹介!
最後までお読みいただき大感謝!みっつでした。